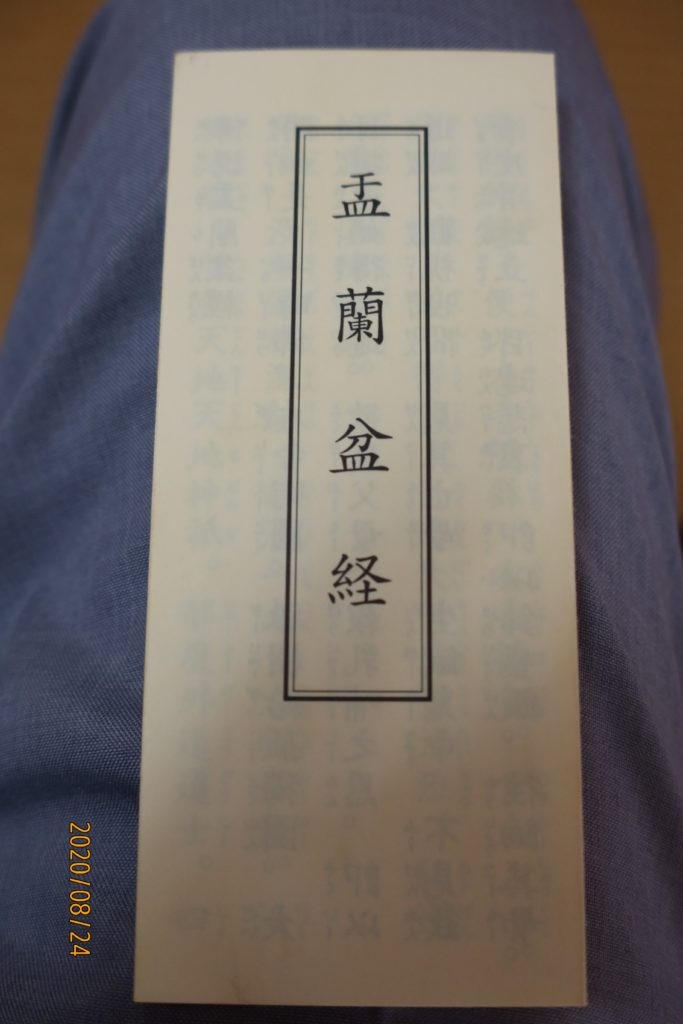みなさんこんにちは
24日の話、後半編です。
早いもので、吉田僧正に来ていただいて、お話しをしていただくのも今年で3年目です。
知らない人の為に、吉田僧正の簡単な紹介を。
実はこの方、元々プロの落語家さんでした、それを結婚された相手がお寺のお嬢さんだったという事で、婿入りでドナドナをされまして、お坊さんになられたわけです。
さすがはプロの落語家、最初の年はご自身のいきさつと、それで密教の教えを面白おかしく話していただいて、みんなにも大人気でした。
吉田僧正、落語家の名前を桂米裕と言います。
そして、実は落語家のお名前だけでなく、お坊さんとしては、本山高野山が認めた、本山布教師の資格も持っておられるのです。
ちなみにこの資格、私も目指しているのですが、まだ私は初心者マークが外れていません。
なかなか、大先輩の背中は遠い!
そして、そんな吉田僧正の今年のお話しは、なんと桃太郎でした。
非常に面白く、そしてわかりやすく語ってくれている内容は、聞いている聴衆がのめり込むようなものでした。
桃太郎というのは、皆さんよくご存知のメジャーな昔話ですが、それを研究されている方もたくさんいらっしゃるようで、いくつか説があるようですね。
おじいさんとおばあさん、語り口調では「ジジ」「ババ」ですが、それは「チチ」「ハハ」が濁ったものだというのが有力なそうで、父母、祖父母に孝行しなさいよ!という教えを言うには非常に良い具合なので、そのまま語り継がれているそうですね。
また、思わずなるほど!と思って頷いてしまったのは、川の上流から桃がドンブラコドンブラコと流れてくるというシーンの意味ですが、川の上流からというのは、おじいさんが種を撒くということをほのめかす表現の技法だそうで。
おじいさん、撒いていたのねw
桃を2つに割って、そこから男の子が飛び出したというものは、桃というのは、女性の足「ふと(もも)」の表現だそうですね。
だから、それを割って出てくる男の子はおばあさんが産んだことになると、、、
それは流石にジジ、ババでは出来ませんね。
このような、思わずなるほど!と思ってしまう内容が、吉田僧正のお話の中にはたくさん詰まっています。
そのお話がどんどん進んでいって、クライマックスに差し掛かると、吉田僧正はこう言います。
実は、桃太郎というお話は中国の儒教思想に大きく影響を受けて作られたお話で、仏教的なお話ではないのです。
では、どうすれば仏教的になるのでしょうか?
こう皆さんに問いかけられて、みんなが考えこむわけです。
さて、皆さんはどうしますか?
桃太郎の結末は、鬼を成敗して、その財宝を持って帰って、おじいさんとおばあさんと一緒に仲良く暮しました、めでたしめでたし。だったと思います。
そこに吉田僧正は仏教的な結末にするのは一つの付け足し、さらに、私達真言宗の教えである密教的にするのは2つの付け足しで事足りるとおっしゃいます。
まず、仏教的な話の結末にするのは簡単です。
桃太郎は鬼を成敗して、その財宝でおじいさんとおばあさん「そして、村のみんなに分け与えて」仲良く暮しました。
これが仏教的です。
自分一人、自分の家族だけ、ではなく、みんなで幸せになりましょう、というお釈迦さまの教えを考えると、なるほど!となりますね。
そして、密教的にするのは、さらにもう一つ
桃太郎は鬼を成敗して、持ち帰った財宝でおじいさんおばあさん、村のみんなと仲良く暮したうえに「敵対した鬼も改心させて、悪事を起こさせないで村で一緒に」幸せに暮しました、めでたしめでたし
これが密教的なお話の結末であると言われました。
みんなで幸せに、その究極は敵も幸せにしたら、敵じゃなくなりますよね?
全ての存在は、仏の優しい心を持っていると言われているので、不可能ではないはずです。
心に仏を宿す=仏の優しい心を宿す、これこそが、私達真言宗の目指すところ、即身成仏です。
死んで仏になるのではなく、生きたまま仏になる、仏を身に宿すことですよ。
と言われて、お話を締めくくりました。
思わず気がつけば、40分という時間があっという間に過ぎてて、非常に楽しい法話でした。
一応要点は書き出したつもりなのですが、本家本元の足元にもおよばません。
なお詳しい話が聞きたい方は、ぜひ吉田僧正に直接会っていただいて、お話を聞いていただくのをおすすめします。
このような、素晴らしい法話も今年で3回目になり、暑い中ではありましたが、無事に御施餓鬼の日を終えることができました。
今年は大変な状況の中でしたが、様々な方の尽力のおかげです。
深く感謝しております、ありがとうございます。
また光明寺をよろしくお願いします。
涼しくなってきたら、またお参りに来てくださいませ